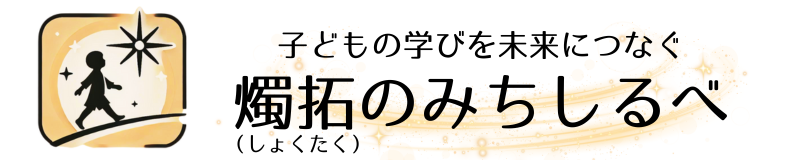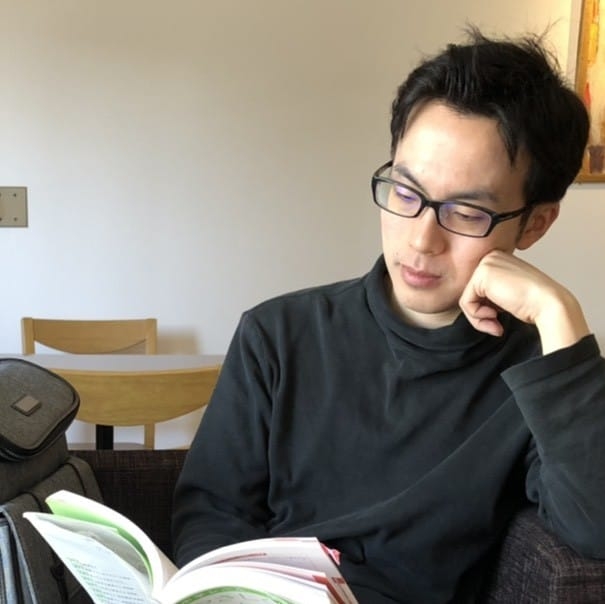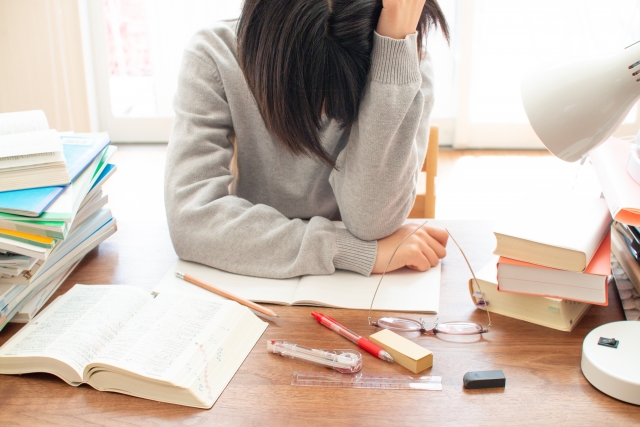大学受験で親が「しんどい」と感じる主な原因
子どもの大学受験は、親にとって単なる学びの通過点ではなく、家族の未来を左右する重大な転換期です。この時期、親たちは子どもの夢と不安が交錯する複雑な感情の渦の中で、強い疲労と大きなストレスに襲われます。
大学受験という子供にとっての最大の荒波の中で、子どもの成長を懸命に支えようとする親の心も、常に緊張と心配で揺れ動いているのは当然です。
経済的な負担、子どもの精神的サポート、高まる期待と不安、そして自身のキャリア経験との比較など、答えのないさまざまな要因が頭の中でグルグルと繰り返し続けることで親はとてつもなく疲れます。
子どもの将来への投資は、単に金銭的な捻出するだけではなく、精神的エネルギーも膨大に消費することを意味しています。自分自身も仕事や家事に追われながら、夜遅くまで勉強する子どもに寄り添い、励まし、時には厳しく、時には優しく導く親の姿は、献身的な愛情を持っていたとしても体力的にも大変です。
年々変化し続ける受験という未知の領域で、親は自身の経験則と子どもの可能性の間で常になにが最善かを考え続けることに苦心しているのが現実です。この繊細な感情の綱渡りが、親にとって最も疲労感と不安を生み出す源泉となっているのはまちがいありません。
そのような中、親自身の体調管理を疎かにしてしまうことで、知らず知らずのうちに心身ともに疲れ切ってしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、親が倒れてしまっては元も子もありません。受験生の子供を支えるためにも、親自身がグッタリしんどくならないよう、しっかりとセルフケアに努めることが大切です。この記事では、大学受験で親が疲れ切らないための7つのコツをご紹介します。親子で健康的に受験期を乗り越えるためのヒントが満載ですので、ぜひ最後までご覧ください。
大学受験で親が「しんどい」と感じている割合と心身の不調
まず、こちらをご覧ください。
受験生の子供を持つ親は受験生以外の子供を持つ親に比べて1.5倍以上もストレスを感じていることが分かります。
| 心の状況 | ①受験生の子ども有 (%) | ②受験生以外の子ども有 (%) | ①/② (倍) |
|---|---|---|---|
| 仕事や家事が手につかない | 18.8 | 13.5 | 1.40 |
| 気がはりつめている | 32.5 | 23.5 | 1.39 |
| 気分が晴れない | 30.8 | 22.5 | 1.37 |
| 物事に集中できない | 23.4 | 17.2 | 1.37 |
| 身体の状況 | ①受験生の子ども有 (%) | ②受験生以外の子ども有 (%) | ①/② (倍) |
|---|---|---|---|
| 頭が重かったり頭痛がする | 21.8 | 15.1 | 1.45 |
| めまいがする | 13.1 | 9.6 | 1.37 |
| 胃腸の具合が悪い | 13.6 | 10.2 | 1.33 |
| 便秘や下痢をする | 22.4 | 17.2 | 1.30 |
| 食欲がない | 9.4 | 7.5 | 1.26 |
出典:10万人調査による「ベネクスリカバリーレポート2023」Vol.2
大学受験で親が「しんどい」と感じる4つの要因
子供の成績や進路への不安
我が子の将来を案じるのは親として当然のこと。しかし、子供の成績が伸び悩んだり、志望校への合格が危ぶまれたりすると、親の不安は募るばかりです。「このままで大丈夫なのか」「もっと何かできることはないか」と、先行きへの不安から心労は絶えません。
受験勉強のサポートによる疲労
受験生をサポートするのは骨の折れる仕事です。学習のペース配分、弱点克服の戦略、体調管理、メンタルケアなど、親としてカバーしなければならない範囲は広範に及びます。毎日のように深夜まで付き合っていると、知らず知らずのうちに疲労が蓄積していきます。
家庭内の雰囲気の悪化
受験勉強に追われる子供は、ともすれば気難しくなりがち。親の言動が余計なプレッシャーを与えていると感じれば、反発することもあるでしょう。会話が減り、すれ違いが増えて、家庭内の雰囲気が悪くなる例は少なくありません。「うちの子はなぜ素直に聞いてくれないんだろう」と悩む親の姿もよく見かけます。
金銭的な負担の増加
大学受験にはお金がかかります。参考書代、塾や予備校の授業料、模試の受験料など、教育費の負担は小さくありません。家計を切り詰めてやりくりしているという話はよく聞きます。金銭面でのストレスから解放されている親は多くないでしょう。
しかし、東京大学の学術機関の論文によると親の教育への関与はプラスの効果があるとした研究もある一方、ほとんど効果がないとした研究もあります。
教育への親の関与(以下、parental involvementとする)について、研究の関心の一層の高まりが見られる。海外の研究では、parental involvementは、子どもの学校選択、進学、学習、学習環境、学校活動参加など様々な観点から検討されており、総じて子どもの教育達成および地位達成にポジティブな影響を及ぼすとの結果が示されている(たとえば、Goodall and Montgomery 2014)、Hango 2007;Hoover-Dempsey and Sandler 1997;Hornby and Lafaele 2011;Jeynes 2017;Mayo and Siraj 2014;See and Gorard 2015;Wilder 2014)
親の関与の形態と学習効果の関連や、子どもの教育達成との明確な関連についての実証的研究の限界についての批判もある。Fan and Chen(2001)は、親の関与に関するさまざまな先行研究の知見は一貫性を欠いているとし、ある研究では、子どもの学習への効果が実証されている一方で、ほとんど効果がないとした研究もあると指摘している。こうした一貫性の欠如の理由には、学校や教員など一時的且つ限定的に関与するアクターと比較して、親の関与は、子どもの生涯にわたって継続されるため、定型化が難しいことが挙げられる。
心をすり減らしてまでサポートしたのに学習効果にほとんど効果がないなんてショックも良いところです。
だからこそ、子どもの成長と合格を願いながらも、ほどよく距離を開けて自身が潰れてしまわないように対策を取っておくことが親子ともども幸せになるポイントです。
親が「グッタリしんどい」とならないための7つのコツ

コツ1:子供の頑張りを認め、褒める
大学受験にとって、親は試合に臨む選手ではなく応援団長です。
この距離感を理解することが何よりも大切です。
そして受験勉強に打ち込む子供を認め、しっかり褒めてあげましょう。
「よく頑張ったね」「努力が実を結ぶといいね」など、前向きな言葉をかけるだけで、子供のやる気を引き出すことができます。
褒められることで、子供は自分の頑張りが親に認められていると実感でき、モチベーションを上げてがんばることができるようになります。
コツ2:子供の話に耳を傾ける
大学受験に望む子供の年齢は20歳に近くなっていますが、まだまだ子供です。
そんな子供の気持ちに寄り添って、悩みに話に耳を傾けることは信頼関係の構築と子どものストレスを下げることに重要な鍵んあります。
受験勉強で悩んでいること、不安に感じていることなど、子供の本音を聞く姿勢を忘れないでください。親が話を真摯に聞いてくれるという安心感は、子供の心の支えになります。
コツ3:適度な息抜きを心がける
真面目な子供ほど勉強漬けの毎日で疲弊しています。
そんな子供を支える親も緊張状態が続いて疲れ果ててしまいます。
だからこそ、意図的に息抜きを取り入れ、リラックスする時間を作りましょう。
好きなことをして過ごす、美味しいものを食べに行く、軽く体を動かすなど、親子でリフレッシュできる方法を見つけてください。
子供が勉強している時は親である自分は休んではいけない。
趣味を楽しんではいけないなど、修行僧のようになってしまう親もいますが、間違っています。
子どものサポーターである親が倒れたら子供も倒れます。
親は自分で自分の心と身体を守ってこそ子供をしっかりサポートできるのです。
コツ4:サポート体制を整える
親だけですべてを抱え込まないことが肝心です。
家族や周囲の協力を仰ぎ、サポート体制を整えましょう。
祖父母に勉強を見てもらう、兄弟に家事を手伝ってもらうなど、周りの助けを借りることで、親の負担を減らすことができます。
主体となるのは間違いなく親であるべきです。
ただ、全部をまるっと抱え込むのではなく、祖父母や兄弟がピンチヒッターとして存在するだけで心はすごく楽になります。
コツ5:金銭面の計画を立てる
教育費の出費については、計画的に対処する必要があります。
授業料の分割払いを利用する、奨学金を活用するなど、目先の出費を抑える工夫が求められます。
長期的な視点に立ち、収支のバランスを考えた金銭計画を立てましょう。
子どものスポンサーである親の金銭面の支援は親の最大のサポートです。
しかし、大学受験は想像以上にお金がかかります。
希望的観測ではなく、現実的な予測を立てて必要なお金を予め準備しつつ、足りない分を補歌目の奨学金や国からの支援金(補助金、助成金、免除など)をしっかり調査して計画しておきましょう。
コツ6:情報収集を効率的に行う
大学受験に役立つ情報は数多くあります。ただ闇雲に情報を集めるのではなく、本当に必要な情報を効率的に収集することが大切です。
予備校の説明会に参加する、先輩の体験談を聞く、信頼できる情報サイトをチェックするなど、目的を持って情報収集に当たりましょう。
特に疲労感は『悩む』ことで大きくなります。
答えのある問いについて頭を使うことが『考える』
答えのない問いについて頭を使うことが『悩む』
悩んでも答えのでないことは情報源のしっかりしたところから情報を集めるか、信頼できる先生に相談するようにして自分の頭から切り離しましょう。
コツ7:自分自身の健康管理を怠らない
子供の健康ばかりを気遣っていると、ともすれば自分自身の健康がおろそかになりがちです。親が倒れてしまっては元も子もありません。
バランスの取れた食事、十分な睡眠、適度な運動を心がけ、自分の健康管理を怠らないようにしましょう。
子供への愛情が深い親ほど子供を優先しがちです。
でも、親が倒れたら子供は勉強どころではありません。
健康は1日でどうこうなるものではないので、日頃から健康に気をつけて行動しましょう。
受験生の親のためのストレス解消法

趣味や運動で気分転換を図る
子供の受験に心を砕いているあまり、自分の時間を持てずにストレスが溜まっているパターンは非常に多いです。趣味の時間を作ったり、軽い運動をしたりと、自分なりのストレス解消法を実践することが大切です。
子供が学校に行っている間にウォーキング、映画、カフェなど気分転換を図ることで、心に余裕を持って子供に接することができるようになります。
同じ立場の親との情報交換
同じように受験生の子供を持つ親との情報交換は、精神的な支えになります。
悩みを共有したり、互いにアドバイスし合ったりすることで、モチベーションを維持することができるでしょう。学校の保護者会や地域のコミュニティを活用するのもよい方法です。
ただし、悪い意味で依存度の高いママ友や他の保護者に引っ張られないようにしましょう。
コミュニティや友人は支え合うものであって、あなたが奉仕する場所ではありません。
メインは子供のサポートであることをお忘れなく。
カウンセリングやセミナーの活用
一人で抱え込むのが辛くなったら、専門家に相談するのも一つの手です。
カウンセラーに悩みを打ち明けたり、セミナーに参加してアドバイスを受けたりするなど、第三者の力を借りることで、ストレスに適切に対処することができます。
大学受験に臨む子供の不安やストレスがダイレクトに伝わって自分が苦しくなる親はたくさんいます。
そんな時は気合や根性で乗り切ろうとせずカウンセリングや心療内科の受診も検討しましょう。
親子で乗り越えるための心構え
子供の自主性を尊重する
親としてついつい口出ししたくなる気持ちはわかります。しかし、子供には子供なりの考えがあるはずです。
「こうしなさい」と言うのではなく、子供の主体性を尊重し、自分で考え、行動できる環境を作ることが大切。子供の自立心を育てることが合格への近道と言えるでしょう。
合格だけでなく成長を見守る
受験は合格が全てではありません。むしろ、受験勉強を通して得られる力の方が大きいと言えます。
忍耐力、計画力、問題解決力など、受験を通して身につけた力は、子供の将来に必ず役立つはずです。合格の先にある子供の成長を信じて、見守ることが親の務めです。
親自身もポジティブでいること
親が不安がったり、ネガティブになったりしていては、子供に悪影響を与えてしまいます。親自身がポジティブな姿勢で臨むことが何より大切。
たとえ受験結果が思わしくなくても、前を向いて歩き続ける強さを子供に示しましょう。親の背中こそ、子供にとって最大の教科書なのです。
まとめ:大学受験を親子で乗り越えるために
大学受験は親子にとって大きな挑戦です。とりわけ親は、しんどさを感じながらも、子供を支える重要な役割を担っています。子供の頑張りを認め、話に耳を傾け、時には息抜きを取り入れるなど、「グッタリ」しないための工夫が大切です。
子どものサポート体制の整備、計画的な金銭管理、効率的な情報収集にも気を配りましょう。そして何より、親自身の健康とポジティブな姿勢を保つことが肝要です。親子で力を合わせ、前を向いて進んでいく。そんな強い絆があれば、受験の壁を乗り越えられるはずです。大学受験に立ち向かう親子の健闘を心から祈っています。