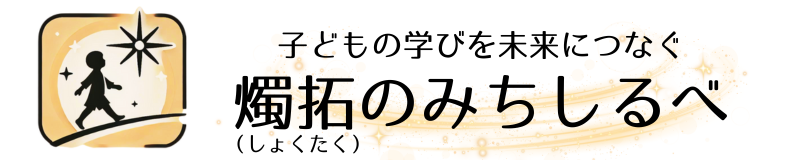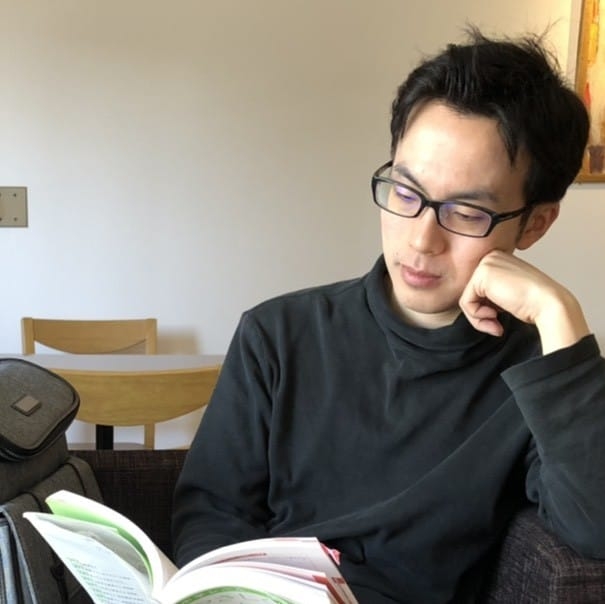「こどもちゃれんじってそろそろ始めた方がいいのかな?」
「うちの子の年齢にはどのコースが合うんだろう?」
と悩んでいるパパ・ママは多いのではないでしょうか。
特に1~3歳ぐらいのお子さんをお持ちの方は、「こどもちゃれんじを始めるなら今が適切な時期なのか」「すでに遅すぎないか」といった不安を抱えているかもしれません。
こどもちゃれんじは0歳から6歳まで年齢別のコースが用意されていますが、実は始める時期によってメリットや注意点が異なります。早すぎても子どもが教材に興味を示さず、遅すぎても学習効果が薄れる可能性もあります。
まず、幼児教育の教材を選ぶ前に知っておくべきポイントをご紹介します。
それが、文部科学省が発表している幼児教育で身につけるべき基礎力です。
文部科学省).jpg)
引用:令和2年5月11日幼児教育の実践の質向上に関する検討会(第9回)(文部科学省)
こちらを見ると、下記3つが挙げられています。
知識及び技能の基礎:体験を通じての気づく力、発見する喜び、感性の基礎
思考力、判断力、表現力等の基礎:予測したり、試したり、工夫するなど考え方の基礎
学びに向かう力、人間力等:協調性、他者を思いやる心などコミュニケーションの基礎
 著者と息子
著者と息子 幼児教育とはそもそも「お勉強」や高い学歴を得るためではなく、社会の中で1人の人間として自立した生活を送っていけるようになるための土台を形成することです。
そのために、こどもちゃれんじを適切に活かすことがポイントとなります。
この記事では、実際に「こどもちゃれんじベビー」「こどもちゃれんじぷち」などを利用した親の口コミや各コースの特徴を徹底分析し、幼児教育で身につけるべき基礎力を養うのに最適な開始年齢についてわかりやすく解説します。
あなたのお子さんにとって最適なタイミングで、最大限の効果を得られるよう、この記事を参考にしてみてください。
- 年齢・月齢別のこどもちゃれんじコースの違いと特徴
- それぞれの年齢から始めるメリット・デメリット
- 後悔しないためのコース選びのポイント
- 子どもの発達段階に合わせた活用方法
こどもちゃれんじは何歳から始めるのが理想的?最適な開始時期を解説
 著者と息子
著者と息子 こどもちゃれんじを始める最適な時期について、結論からいうと「0〜2歳」が最も効果的といわれています。しかし、各家庭の状況や子どもの発達状況によって、最適なタイミングは異なります。
まずは、各年齢向けコースの特徴と内容を見ていきましょう。
こどもちゃれんじベビー(0〜1歳)の特徴と内容
こどもちゃれんじベビーは、0〜1歳児向けのコースで、赤ちゃんの成長に合わせたおもちゃや絵本が届きます。実は0ヶ月の新生児から始めることができ、月齢ごとに細かく設計されています。
0ヶ月から5ヶ月までの赤ちゃんには「特別号」というものがあり、人気の高い「五感で楽しむ6wayへんしんしんジム」が付いてきます。このベビージムは市販で購入すると5,000円以上するものが、約2,000円で手に入るため大変お得です。
また、毎月届く教材内容は次のような流れになっています:
- 0〜5ヶ月:五感で楽しむ6wayへんしんジム、絵本「タンタンタン」など
- 6ヶ月:「しまじろうのおきあがりこぼし」、「五感で楽しむアクティビティBOX&マット」など
- 7ヶ月:「かみかみもぐもぐ布えほん」など
- 8ヶ月:「でるでるキューブ&くるくるキューブ」など
このように、月齢ごとに赤ちゃんの発達段階に合わせたおもちゃが届くので、「この月齢にはどんなおもちゃが適切か」を自分で考える手間が省けます。特に初めての育児で忙しい親にとっては、プロが選んだ月齢に合った教材が自動的に届くのは大きな魅力です。
ただし、このコースにはデメリットもあります。複数の親からの口コミでは「毎月届く教材の豪華さにばらつきがある」「物足りないと感じることがある」といった声も。しかし、月齢に合わせたおもちゃが定期的に届くことで、赤ちゃんの五感を刺激し、発達を促進する効果は大きいといえるでしょう。
こどもちゃれんじぷち(1〜2歳)はどんな内容?

1歳からのこどもちゃれんじぷちは、「歩く・話す・考える」など、1〜2歳児特有の発達を促す教材が中心です。こどもちゃれんじベビーよりもさらに「自分でやってみる」活動が増え、知的好奇心を刺激する内容になっています。
ぷちコースでは、次のような教材が届きます:
- 「しまじろうといっしょ!おはなしだいすき」などの絵本
- 「ころがしてポン!」「しまじろうのおしゃべりでんわ」などの知育玩具
- 簡単な言葉遊びや指先の発達を促すおもちゃ
1歳頃になると、子どもは自分の意思を表現するようになり、おもちゃへの好みもはっきりしてきます。そのため、こどもちゃれんじぷちの教材は、子どもが「自分でやってみたい」と思えるような仕掛けが多く含まれています。
ベビーからぷちへの移行タイミングについては、1歳の誕生日前後が一般的です。ただし、子どもの発達には個人差があるため、以下のような様子が見られる場合は、ぷちコースへの移行を検討するタイミングかもしれません。
- 簡単な言葉を話し始めた
- 一人で立ったり、歩いたりできるようになった
- おもちゃで「こうしたい」という意思表示ができる
- 指先を使った細かい動作に興味を示す
 著者と息子
著者と息子 私は自分の子以外にも甥っ子を3人見てきた経験で言えば、「ベビーコースよりもぷちコースの方が子どもの反応が良くなった」と感じました。
実際、1歳を過ぎると好奇心が一層高まり、自分でチャレンジすることへの喜びを感じるようになるため、ぷちコースの内容が子どもの発達状況とマッチしやすくなります。
2歳からこどもちゃれんじを始めるメリット・デメリット
2歳からこどもちゃれんじを始める場合、「ぷち」(1〜2歳向け)か「ぽけっと」(2〜3歳向け)かの選択になります。この時期から始めることには、いくつかの特徴的なメリットとデメリットがあります。
- 子どもの好みや興味がはっきりしているため、教材の活用率が高まりやすい
- 言語理解力が発達しているため、教材の説明を理解して主体的に取り組める
- 親の余裕ができてきて、一緒に取り組む時間を確保しやすい
- 子どもの発達状況を見て、より適切なコースを選べる
しかし、デメリットもあります:
- すでに0〜1歳期の発達に最適なおもちゃや経験を逃している
- 特に英語教育においては、「英語耳」を形成する最適期間の一部を逃している可能性がある
- 継続するコース数が少ないため、総合的なコスパは下がる
2歳児の発達段階を見ると、言葉の習得が急速に進み、思考力や想像力も豊かになってくる時期です。「ごっこ遊び」や「模倣」が好きになり、教材を使って親子でコミュニケーションを取りながら遊ぶことで、より効果的な学びになります。
 著者と息子
著者と息子 2歳からこどもちゃれんじを始める場合のコース選択ですが、子どもの発達状況によって異なります。比較的言葉の発達が遅い場合や、まだ細かい手先の動きが苦手な場合は「ぷち」コースから始めるのも一つの選択肢。
逆に、すでに多くの単語を話し、指先を使った遊びも上手な場合は「ぽけっと」コースからスタートするのがおすすめです。
知人の2歳の男の子のママは「言葉の発達が少し遅かったので、ぷちコースから始めましたが、言葉を覚えるスピードが格段に上がった」と話しています。また別の2歳3ヶ月の女の子のパパは「ぽけっとのおもちゃが大好きで、以前より集中して遊べるようになった」と語っています。
子どもの発達に合わせた教材選びのポイント
こどもちゃれんじを選ぶ際に最も重要なのは、単に年齢だけでなく「我が子の発達状況に合っているか」という視点です。発達には個人差があるため、月齢や年齢だけを基準にするのではなく、子どもの興味や能力に合わせて選ぶことが大切です。
教材選びの重要なポイントとして、次の3つを挙げられます:
- 子どもの現在の興味や関心に合っているか
- 言葉に興味があるなら言葉を育てる教材
- 手先の器用さを伸ばしたいならパズルなどの教材
- 体を動かすことが好きなら、動きを促す教材
- 子どもの発達段階に適しているか
- 難しすぎず、簡単すぎない適度な難易度
- 成功体験が得られる内容
- 少し先の発達を促す要素が含まれている
- 親の教育方針との一致
- 家庭で大切にしている価値観と合っているか
- 親自身が無理なく継続できる内容か
- 子どもと一緒に楽しめる内容か
実際、こどもちゃれんじを選ぶ際は、公式サイトの資料請求で教材見本やDVDが無料でもらえます。これを活用して、実際に子どもの反応を見てから入会を決めるのも良い方法です。
また、兄弟姉妹がいる場合は、上の子の使っていた教材に下の子が興味を示すこともあります。そういった場合は、下の子の年齢より少し上のコースを選ぶという選択肢もあるでしょう。
子どもの発達に合わせた教材選びで大切なのは、「今できること」と「もうすぐできそうなこと」のバランスです。あまりにも簡単だと子どもは飽きてしまいますし、難しすぎると挫折感を味わいます。適度な「できた!」という成功体験と「もう少し!」というチャレンジ要素が含まれた教材が理想的です。
こどもちゃれんじの年齢別コース徹底比較!選ぶ前に知っておくべきこと
こどもちゃれんじには年齢別に複数のコースがありますが、それぞれのコースにはどのような特徴や違いがあるのでしょうか。ここでは、年齢別コースの内容や特徴を詳しく解説し、選ぶ際のポイントをご紹介します。
こどもちゃれんじベビー(1歳以降)の内容と評判
こどもちゃれんじベビーは1歳11か月まで受講できますが、特に1歳以降の内容はどうなっているのでしょうか。1歳になると、おもちゃの種類や内容も変わってきます。
1歳以降のベビーコースで届く主な教材は次のとおりです:
- 1歳:「ころりんメロディーケーキ」、絵本「みいちゃん いいこいいこ」など
- 1歳1ヶ月:「しまじろうのおやすみトイ」、絵本「ね〜んねねんね」など
- 1歳3ヶ月:「1さいの みずあそびセット」、絵本「じゃばじゃば ばっしゃーん」など
- 1歳6ヶ月:「まるちゃんパズル」、絵本「まんまるまるちゃん」など
- 1歳9ヶ月:「みずでおえかきセット」、絵本「このせんなぁに?」など
特に1歳半の子どもに適した教材としては、手先の発達を促す「まるちゃんパズル」や、指先を使って遊ぶ「いろのさかなつりセット」などが好評です。この時期は、子どもの指先の発達が進み、「つまむ」「はめる」「引っ張る」などの動作ができるようになってくるため、そういった動きを促す教材が中心となっています。
実際に使った親の口コミでは、「1歳半頃からおもちゃへの興味が明らかに増した」「教材を使って遊ぶ時間が長くなった」という声が多く聞かれます。特に、水遊びや色の認識を促すおもちゃは子どもの反応が良いようです。
ねんねーが流暢だなーと思ったらしまじろうのおやすみトイのいっしょにねんねー!を真似してるんだなって思ったらしまじろうに感謝しかないな…そろそろやめようかなー?と思ってたけど継続して様子みるか… pic.twitter.com/Su2qlAz4dO
— む ぎ︎ ☺︎ 2 y 🧸 (@mugicho_co) March 17, 2024
だいぶ遅くなりましたが💦始めます!
《こどもちゃれんじbaby》
・いろのさかなつりセット
魚は全て振るとシャラシャラ音がする。前月号のまるちゃんパズル裏が魚の池になって遊べます。2歳まではよく魚釣りしてた。今ではおままごとに魚を使うが本来の遊び方はさすがにもうしてない。 https://t.co/rf7EnAEAgV pic.twitter.com/SrkC0NHbQG— おこの (@outino_koto) February 2, 2025
ある1歳半の女の子のパパは、「最初は興味を示さなかったおもちゃも、数週間後に突然夢中になって遊び始めたことがあった」と語っています。子どもの興味は突然芽生えることもあるので、すぐに反応がなくても諦めずに定期的に遊びを提案することが大切です。
また、1歳の誕生日には特別号として「歌って♪おしゃべりしまじろう」「かたちあそび知育ケーキ」などの豪華な特典がもらえるのも魅力の一つです。ただし、この特別号は自動で届くわけではなく、お誕生月の翌月5日までに(お誕生日までに受け取りたい場合は、1歳になる前月22日までに)申し込み手続きが必要なので注意が必要です。
こどもちゃれんじベビーを始めて後悔する理由とは?
こどもちゃれんじベビーは多くの家庭で支持されていますが、中には「始めて後悔した」という声もあります。主な後悔ポイントとその対策を見ていきましょう。
1. 教材の収納スペースの問題
毎月届くおもちゃや教材の収納に困るという声があります。特に住居の収納スペースが限られている家庭では、これが大きな問題になることも。
「部屋が狭いので、毎月届く教材の置き場所に困っています。でも、実際はひとつひとつは小さなものが多いので、工夫次第で何とかなります」(5歳児ママ)
対策としては、使わなくなったおもちゃは思い切って処分する、収納ボックスを活用する、親戚の子どもにおさがりとして譲るなどの方法があります。
2. コスパや教材の質に関する不満
月によって届く教材に当たり外れがあると感じる人もいます。「今月はすごく良かったけど、来月はちょっと…」という温度差を感じることがあるようです。
「水遊びのおもちゃなんて100円ショップでも買えるのに…と思うことがあります。でも、月齢に合った遊び方を知れるのは価値があると思っています」(0歳児パパ)
この点については、「おもちゃ自体の価値」だけでなく「その月齢に適した遊びを教えてもらえる価値」も含めて考えるとコスパは悪くないという意見も多いです。
3. 自動継続による料金上昇への不満
こどもちゃれんじは退会しない限り自動継続するシステムで、学年が上がるごとに受講費が増加します。たとえばベビーは月額1,990円〜(18回分一括払いの場合)ですが、年長向けのじゃんぷは月額2,730円〜(12ヶ月分一括払いの場合)まで上がります。
「自動更新で高校3年生まで継続することに驚きました。でも、いつでも解約できるので、必要なときだけ受講するという選択もできるからまぁいいかと思ってます」(1歳児パパ)
これについては、各段階でしっかり見直しをして、必要なコースだけを受講するという方法が有効です。退会はいつでも可能で、一括払いをしていても返金されるので安心です。
4. 特典をもらい損ねる
申し込み期限を勘違いして特別号や追加特典がもらえなかったという後悔も多く聞かれます。特に豪華なベビージムがもらえる特別号は人気が高いため、逃すと大きな後悔につながります。
「忙しさにかまけて手続きを忘れ、1歳の誕生日特別号をもらい損ねました。
案内はしっかりチェックすべきでした」(1歳児ママ)
特典の申込期限は次のようになっています:
- 入会特典:生後4ヶ月になる月の12日まで
- 特別号申し込み:生後5ヶ月になる月の12日まで
- 1歳の誕生日特別号:誕生日の翌月5日まで
後悔しないためには、これらの期限をしっかり確認し、早めに申し込むことが大切です。
こどもちゃれんじは絵本だけでも価値がある?
こどもちゃれんじでは毎月おもちゃと一緒に絵本も届きますが、「実はこの絵本が一番の価値」と感じている家庭も少なくありません。こどもちゃれんじの絵本の特徴と価値を見ていきましょう。
絵本の特徴と質
こどもちゃれんじの絵本は、以下のような特徴があります:
- 月齢・年齢に合わせた内容と難易度
- 子どもの発達段階に合わせた仕掛けや工夫
- 親しみやすいキャラクターを通した学び
- 日常生活や季節の行事と連動した内容
特に0〜1歳向けの絵本は、シンプルでわかりやすい内容ながら、子どもの興味を引く工夫が満載です。例えば、7ヶ月向けの「よいしょ こらしょ」は、まだ言葉の少ない赤ちゃんでも楽しめるリズミカルな言葉遣いが特徴です。
市販の絵本と比較すると、一冊あたりの価格は高くなる可能性がありますが、子どもの発達段階に合わせて選ばれているという点で価値があります。
絵本のみで利用する方法
「おもちゃよりも絵本が気に入った」「うちの子は絵本が大好き」という場合は、こどもちゃれんじの絵本だけを活用するという選択肢もあります。
「毎月届く絵本を楽しみにしています。おもちゃは興味を示さないものもありますが、絵本はいつも喜んで何度も読んでと持ってきます」(1歳児ママ)
絵本のみを効果的に利用するコツとしては:
- 毎日決まった時間に読む習慣をつける
- 絵本の内容に合わせた簡単な遊びを取り入れる
- 親子の対話を大切にしながら読む
- 子どもの反応を見ながら、同じ絵本を繰り返し読む
おもちゃと絵本の価値比較
おもちゃと絵本、どちらに価値があるかは子どもの個性や家庭の方針によって異なります。おもちゃは手や体を使った遊びを通して発達を促し、絵本は言葉や想像力を育てます。
 著者と息子
著者と息子 私も息子に絵本を読み聞かせても興味を持ってくれなかったんですが、息子の手の届くところに雑然と絵本を置いてたら、勝手にめくって遊ぶようにリ、気づいたら、絵本を持ってきて読むよう催促してくるようになりました。
そこからは、毎日絵本を読み聞かせていると一気に言葉を覚えだしたので、絵本が最も価値があったんじゃないかと思います。
これは絵本の持つ長期的な教育効果や、何度も繰り返し楽しめるという特性によるものでしょう。
おもちゃは成長とともに興味が薄れることもありますが、絵本は成長に合わせて楽しみ方が変わり、長く活用できるというメリットがあります。特に言葉の発達が著しい1〜2歳頃は、絵本の価値がより高まる時期といえるでしょう。
こどもちゃれんじを始める前に知っておきたい実践的アドバイス
こどもちゃれんじを最大限に活用するためには、単に教材を受け取るだけでなく、家庭での取り組み方や環境づくりも重要です。ここでは、実際にこどもちゃれんじを活用している家庭からの実践的なアドバイスをご紹介します。
兄弟姉妹がいる場合の年齢別活用法
兄弟姉妹がいる家庭でこどもちゃれんじを始める場合、第1子と第2子以降では状況が大きく異なります。効果的な活用法を見ていきましょう。
第1子と第2子以降での違い
第1子の場合は、親も子どもも初めての経験なので、教材を通して「この月齢・年齢では何ができるのか」「どんな遊びが適切か」を学べるメリットがあります。一方、第2子以降では、上の子の経験から親の知識も増え、また上の子のおもちゃが既に家にあることが多いため、新たに同じようなおもちゃが届いても価値を感じにくいこともあります。
「上の子のときは毎月楽しみに開封していましたが、下の子では『これ、似たようなおもちゃあるよね』と感じることもありました」(2児のパパ)
ただし、年の差が大きい場合や、男女差がある場合は、第2子以降でも新鮮さを感じられることがあります。
兄弟での教材共有のコツ
兄弟で教材を共有する場合のコツとしては:
- 上の子には「教える」役割を与える
- 下の子専用の時間を作り、その間だけ新しい教材を使わせる
- 兄弟で楽しめるようなルールを作る(例:午前中は下の子、午後は上の子が優先など)
- 上の子には「お兄ちゃん・お姉ちゃん用」の特別感を出す工夫をする
実際、多くの家庭では年齢の近い兄弟がいる場合、年齢の高い子向けの1つのコースを契約し、兄弟で共有するというスタイルを選んでいます。これはコスト面でも効率的ですが、下の子には少し難しい内容になる可能性があるため、親のサポートが必要です。
年齢差がある場合の対応策
年齢差が3歳以上ある場合は、それぞれの年齢に合ったコースを選ぶのが理想的です。しかし、経済的な理由から1つのコースしか選べない場合は、次のような工夫が考えられます:
- 下の子の年齢に合わせたコースを選び、上の子には別の学習教材や絵本を用意する
- 上の子の年齢に合わせたコースを選び、下の子には親がサポートしながら一部の活動だけ参加させる
- 両方の年齢の中間的なコースを選び、それぞれに難易度を調整して活用する
ある4歳と1歳の兄弟がいる家庭では、4歳児向けの「すてっぷ」を契約し、1歳の弟には簡単なおもちゃや絵本の部分だけを活用。同時に、過去の「ぷち」のおもちゃも取っておいて、弟が遊べるようにしているそうです。
こどもちゃれんじを最大限活用するための親の関わり方
こどもちゃれんじの効果を最大化するためには、親の関わり方が非常に重要です。特に小さな子どもの場合、親がどう接するかで学習効果が大きく変わってきます。
親子で一緒に取り組む重要性
こどもちゃれんじは単なる「おもちゃ」ではなく、親子のコミュニケーションツールとしての役割も持っています。特に0〜2歳の子どもは、親と一緒に取り組むことで学習効果が高まります。
「最初は『遊ばせておけばいい』と思っていましたが、一緒に遊ぶことで子どもの反応が全然違うことに気づきました。親子の時間としても貴重です」(1歳児ママ)
親が積極的に関わることで、子どもは安心して新しいことに挑戦でき、また親の反応を見ながら「これは面白いものなんだ」と学ぶこともできます。忙しい日々の中でも、短時間でも集中して一緒に取り組む時間を作ることが大切です。
毎日の習慣化のコツ
こどもちゃれんじの公式サイトでは「入園前は1日20分ほど」の取り組みが推奨されていますが、これを習慣化するコツとしては:
- 決まった時間に取り組む(例:お昼寝の後の30分など)
- 子どもの機嫌が良い時間帯を選ぶ
- 親も一緒に楽しむ姿勢を見せる
- 無理に長時間やらず、子どもが飽きる前に終える
- 今日は絵本、明日はおもちゃなど、日によって変化をつける
特に重要なのは「毎日少しずつ」という継続性です。1日に長時間取り組むよりも、毎日短時間でも継続することで、子どもの中に学習習慣が自然と身についていきます。
教材を長持ちさせる工夫
こどもちゃれんじの教材を長持ちさせ、価値を最大化するコツとしては:
- 使わないときは専用の箱や袋に片付ける
- 小さなパーツは分類して保管する
- シールやカードなどは専用のファイルで管理する
- おもちゃごとに「出番」を決めて、全てを一度に出さない
- 親が使い方を理解し、適切な遊び方を子どもに教える
特に「全てを一度に出さない」というのは多くの家庭で実践されている方法で、2週間に1回程度新しいおもちゃを出すようにローテーションすることで、子どもの飽きを防ぎ、教材への興味を持続させることができます。
また、親向けの情報誌やアプリを活用することで、教材の効果的な使い方を知ることができます。特に「しまじろうクラブ あそびコンシェルジュ」アプリでは、成長に合った遊び方や関わり方が紹介されており、多くの親に役立つ情報が提供されています。
年齢別に見るこどもちゃれんじの費用対効果
こどもちゃれんじは教育投資としても考えられますが、年齢によって費用対効果は異なります。それぞれの年齢から始めた場合の費用と効果を比較してみましょう。
0歳、1歳、1歳半、2歳からの費用比較
こどもちゃれんじの料金は年齢によって異なります:
- こどもちゃれんじベビー(0〜1歳):月額1,990円〜(18回分一括払いの場合)
- こどもちゃれんじぷち(1〜2歳):月額2,460円〜(12ヶ月分一括払いの場合)
- こどもちゃれんじぽけっと(2〜3歳):月額2,460円〜(12ヶ月分一括払いの場合)
また、子どもの生まれ月によって受講できる期間も変わります。例えば4月生まれの子は1歳11ヶ月号まで受講できますが、3月生まれの子は1歳号までの受講になります。
費用面で見ると、早く始めるほど総額は高くなりますが、1回あたりの単価は安くなる傾向があります。例えば、0歳の4月から始めると18回分で35,820円(1回あたり1,990円)ですが、3月生まれで0歳から始めると7回分で15,652円(1回あたり2,236円)となります。
長期的に見た経済的メリット
経済的な観点からは、次のようなメリットが考えられます:
- 市販のおもちゃをあれこれ買うより、月齢に合ったものが定期的に届くほうがムダが少ない
- 特別号などの特典は市販品より割安で手に入る
- 長く続けることで兄弟姉妹での共有や、おさがりとしての価値も生まれる
特に0〜1歳は発達が著しく、適切なおもちゃを親自身で選ぶのは難しい時期です。その点、プロが選んだ教材が定期的に届くというのは、たとえ月々の費用がかかっても長期的には効率的な投資と言えるでしょう。
また、言葉を覚える時期に、楽しみながら思考力の基礎を同時に学べることは将来の大きな糧になります。
こちらは、鳴門教育大学大学院高度学校教育研究科の泰山先生が示されている思考スキルの定義になります。
ぜひ見てください。
【思考スキルの教科横断的な活用による思考力育成:高知県】.jpg)
引用:教科共通の思考スキルとその定義(泰山ほか2014)【思考スキルの教科横断的な活用による思考力育成:高知県】
 著者と息子
著者と息子 一口に『思考力』と言ってもこれだけの種類があります。
これらを自然な形で早い時期に身につけられることが、ほんとうの意味で賢い子に育つポイントになります。
しかし、これらのスキルを身につけるために親御さん自身が適切な教材を選ぶとなると至難の業です。
だからこそ幼児教育教材があると非常に効率的です。
他の知育教材との比較
市場には様々な知育教材やサブスクリプションサービスがありますが、こどもちゃれんじの特徴としては:
- 長年の実績と研究に基づいた教材設計
- おもちゃだけでなく、親向けの情報や子どもの成長記録機能などの充実
- しまじろうというキャラクターを通じた一貫した学び
- イベントや英語教材などの関連コンテンツの充実
例えば知育玩具のレンタルサービスと比較すると、こどもちゃれんじはおもちゃを所有できるメリットがあります。また英語教材と比べても、日本の季節や文化に根ざした内容が含まれているという特徴があります。
あるママの声では「他の知育サブスクも試したけれど、こどもちゃれんじは子どもが自分のものとして愛着を持って遊ぶ姿が印象的だった」とのこと。所有することの価値も、この教材の特徴の一つと言えるでしょう。
まとめ:こどもちゃれんじは何歳から始めるのが最適か
ここまで様々な角度からこどもちゃれんじについて見てきましたが、「何歳から始めるのが最適か」という問いに対する答えをまとめてみましょう。
年齢別の開始メリットまとめ
- 0歳(ベビー)から始める場合
- 五感の発達を促す教材が手に入る
- ベビージムなどの特別号が利用できる
- 親自身も赤ちゃんの発達について学べる
- 早期から教育的な関わりの習慣ができる
- 1歳(ぷち)から始める場合
- 言葉や手先の発達を促す教材が充実
- 子どもの好みや興味がはっきりしてきて活用しやすい
- ベビー期より親の余裕ができて一緒に取り組みやすい
- 2歳(ぽけっと)から始める場合
- 知的好奇心が高まり、教材への反応が良くなる
- 指示を理解して遊べるようになる
- より高度な思考力や創造力を育む教材が活用できる
実際のところ、子どもの発達状況や家庭環境、親の教育方針によって「最適な開始年齢」は異なります。どの年齢から始めても、それぞれにメリットがあります。
子どもの個性に合わせた選び方
最も大切なのは、年齢だけでなく「我が子の個性や発達状況」に合わせて選ぶことです。
例えば:
- 活発で体を動かすのが好きな子 → 動きを促す教材が多いコースを選ぶ
- 絵本が大好きな子 → 絵本の内容を重視したコース選び
- 手先が器用な子 → より細かい操作を必要とする教材のあるコースも検討
また、親自身の余裕や関わり方も重要な要素です。忙しい時期に高度な教材を始めても十分に活用できないかもしれません。まずは親子で無理なく継続できるコースから始めるのも一つの方法です。
迷ったときの判断基準
「結局いつから始めればいいの?」と迷った場合は、次の基準で判断するとよいでしょう。
- まずは資料請求で教材サンプルを確認し、子どもの反応を見る
- 今の子どもの興味や発達段階に合った内容かどうかを優先する
- 親自身が無理なく継続できる環境を考慮する
- 長期的な教育投資として考え、早めに始められるなら早めに
多くの親が「もっと早く始めればよかった」と感じることはあっても「早すぎた」と後悔することは少ないようです。特に特別号や入会特典は期限があるため、興味があるなら早めの検討がおすすめです。
「うちは1歳半から始めましたが、子どもの発達が早く、もう少し早く始めればよかったと思いました。でも、実際にやってみないとわからないものですね」(2歳児パパ)
 著者と息子
著者と息子 最終的には、「子どもが楽しんで取り組めるか」「親子の時間として価値があるか」という視点で選べば、きっと満足のいく選択ができるでしょう。それぞれの家庭に合った最適なタイミングで、こどもちゃれんじの旅を始めてみてください。
子どもの成長は一瞬です。どの時期から始めるにせよ、親子で楽しみながら取り組むことで、かけがえのない思い出と子どもの確かな成長につながることでしょう。