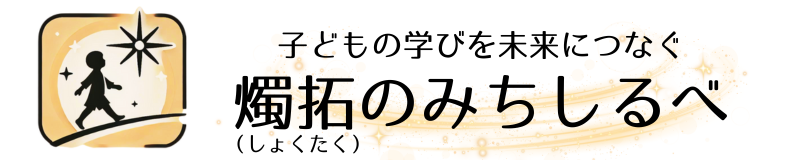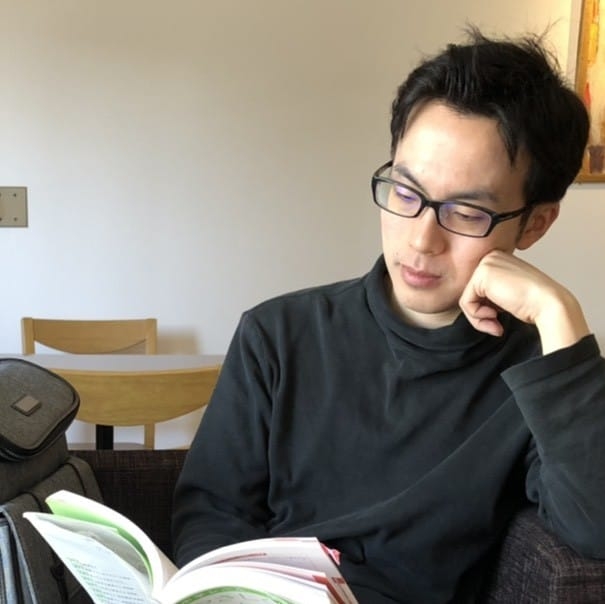小学校受験は、親子にとって大きな挑戦です。
初めて受験を考えている親は、「何から始めれば良いのか」、「準備に抜けがないだろうか」と不安を感じることも多いはずです。本記事では、その不安を解消し、小学校受験の準備から注意点までを導入します。
1. 小学校受験の基礎知識 小学校受験とは?
小学校受験は、子どもの知能、行動観察能力、表現力を総合的に試す考査です。
学校ごとに試験内容や基準が異なるため、一般的な準備に加えて、志望校ごとの対策が必要です。
例えば、知能試験では、図形を完成させるパズル問題や、数字や言葉の並び替え問題がよく出題されます。
行動観察試験では、集団活動の中でルールを守りながら協力できるかどうかを見られることが多いです。
表現力の試験では、子どもがテーマについて自分の考えを述べたり、簡単なプレゼンテーションを行う場面があります。
それぞれを具体的に見ていきましょう。
受験で求められる能力
1.知能試験: 図形、数値、言語に関する問題
例えば、図形を組み合わせて特定の形を作る問題や、簡単な数の計算問題などがあります。
これらは、論理的思考力や注意力を評価します。
具体的には、車の数を数えたうえで合計何台あるか、
三角形と四角形を組み合わせて特定の形を作れるかなどです。
また、短い文章を声を出して読んでもらい、概要を問うなど行います。
2.行動観察: ルールに従って行動できるか
子どもが与えられたルールに従って行動できるか、また他の子どもと協力して課題を達成できるかを見ます。
例えば、ブロック遊びを通じてリーダーシップや協調性を判断することがあります。
これは、リーダーになれたら合格というのではなく、他の子供と協調して物事に取り組めるかを判断しているので、独りよがりな行動を取ったりせず、チームワークが取れるかを見ています。
3.表現力の試験: ディスカッション力、情報伝達力
「好きなものについて話してください」という簡単な質問から、グループでテーマを議論して結論を出すような課題まで、さまざまな形式で行われます。これにより、子どもの自己表現能力や他者への情報伝達力が測定されます。
これは、自分の考えや思ったことを拙くても良いので、ハッキリと伝えられるかというコミュニケーション力を見ています。
小学校受験では、これらの能力をバランスよく伸ばすことが重要です。
家庭での学習や日常生活での経験が、これらの能力の向上に直結します。
では、具体的にどのようにこれらの能力を向上させられるのかお伝えします。
2. 小学校受験対策を始める時期とスケジュール管理
小学校受験の準備はいつから?
小学校受験の準備は、早ければ早いほど良いとされています。
しかし、あまりにも早くお受験モードで始めて子どもに負担をかけるのではなく、子どもが楽しみながら取り組みながら、気づいたら自然と勉強に取り組んでいるような流れがベストです。
そのため、適切なタイミングで少しずつ対策を進めることが大切です。
小学校に上る1年前(年長さん)からでも準備を整えることは可能ですが、急なお受験モードへの変更に子どもがストレスを感じやすいので、理想の流れをご紹介します。
小学校受験に向けての理想的なスケジュール
(1)3~4歳:言葉が話せるようになってきたタイミング
難関大学の付属小学校に合格するような家庭はこの頃から準備を始める方がほとんどです。
この時期は、幼児教室と家庭学習を併用し、子どもの好奇心を刺激しつつ、他の子どもとの触れ合いの中での集団行動に慣れることを中心とした対策を行います。
具体的には、以下の内容に取り組みましょう。
●絵本を読み聞かせ、語彙力や表現力を高める:
毎日寝る前に絵本を読み聞かせ、物語の内容について親子で話し合う時間を設けます。
尋問しているようにはならないように注意しながら、絵本の内容について質問したりどんな気持ちだったのかを自分の言葉で話すように促しましょう。
●知育玩具やパズルで遊びながら、思考力や空間認識能力を育む:
図形パズルや積み木、ブロック遊びなどを積極的に取り入れ、遊びを通して自然と学習できる環境を作ります。
子どもは、『壊す』ことは得意ですが、『作る』ことは苦手です。
だから、手に積み木を持たせて、まずは2段重ねてみたり、おもちゃを2つ重ねてみたりするなど、遊びながら作ることで空間認識能力を育みましょう。
●公園で遊ぶ、散歩をするなど、体力づくり:
外遊びを通して、基礎体力の向上に努めることも大事です。
子どもの成長には五感の刺激が欠かせません。
この時期は、家の中の学習が3割、外での体力づくりが7割とお考えください。
●日常生活の中で、マナーやルールを教える:
食事のマナーや挨拶、公共の場でのルールなど、基本的な生活習慣を身につけさせました。
難しく考える必要はありません。
朝起きた時の『おはよう』
ご飯を食べる前の『いただきます』
目上の人に会った時の『こんにちは』
こういったマナーやルールを身につけておけば受験の際にも自然にできるようになります。
(2)5歳:年中開始
周囲環境に学習の習慣を取り入れつつ、読み書きになれさせましょう。
たとえば、日常的に絵本を読む習慣にプラスして、簡単な言葉遊びや数遊びを取り入れましょう。
市販のドリルを使って文章の内容を言葉で伝えるだけでなく、文字で書く練習や、スペース内に書く意識付けを始めましょう。
子どもに大人ほどの集中力は期待してはいけません。
30分集中して30分休むを1セットに午前、午後と1セットずつできるように取り組んでみましょう。
くれぐれも強引に学習させるのではなく、子どもが学びに興味を持つきっかけを作ることが大切です。
(3)6歳:年長開始
本格的な受験対策の開始です。受験レベルに近い出題形式の問題にチャレンジしてみましょう。
市販されている受験用教材や問題集を使い、模擬問題に触れ始めましょう。
この時期には、子どもの得意分野や苦手分野を把握し、計画的に補強することが重要です。
また、家庭内で小テスト形式の遊びを取り入れることで、楽しみながら学べる工夫も有効です。
そうは言ってもまだ幼稚園児です。
受験生という言葉の意味も理解できていない子もたくさんいます。
いつもより少し多めに勉強して、いっぱい褒めることで、子どもが苦痛にならないように心がけましょう。
(4)3ヶ月前:直前期
実践的に過去問にチャレンジし始める時期です。
模擬試験や受験会場を意識した実践的な練習を行います。
たとえば、志望校の試験形式に合わせた練習問題を解かせたり、面接のロールプレイを親子で行うと効果的です。
また、この時期には子どもの集中力を高めるために、試験時間に合わせた問題演習と適切な休息とメリハリのあるスケジュール管理も欠かせません。
このような段階的な準備を進めることで、子どもに無理なく力をつけ、受験本番への自信を育てることができます。
3. 小学校受験のための具体的な準備
子どもの学習対策
1.教材選び: こども向けの図形問題集、パズル問題
具体的な教材としては、子ども向けの図形問題集やパズル問題がおすすめです。
たとえば、簡単な形を組み合わせて図形を完成させる問題や、視覚的な判断力を鍛える迷路問題などがあります。
これらの教材は、遊び感覚で取り組むことができるため、子どもが楽しく学べます。
2.家庭学習: 日々のルーティングの実践
日々の家庭学習では、生活の中にルーティンを作ることが重要です。
たとえば、朝の10分間に数字や文字を書かせる練習を取り入れる、食事後に親子で読み聞かせを行うといった具体的な習慣づけが効果的です。
また、図形や言葉遊びを親子で楽しむ時間を作ることで、自然に知識が身につきます。
3.過去問の活用: 学校別のプレテストを経験
受験前には過去問を活用しましょう。
たとえば、志望校の過去問に似た形式の模擬試験に参加することで、試験の雰囲気や緊張感に慣れることができます。
また、親がその結果を分析し、子どもの強みや弱点を把握して次の対策に活かすことができます。
過去問の活用方法の注意
過去問は、単に解答するだけでなく、以下の点に注意して活用しましょう。
・時間配分の練習: 実際の試験時間を意識し、時間内に問題を解き終える練習をします。
・解答方法の確認: 正解だけでなく、解答に至るまでの過程を丁寧に確認し、子どもに理解できるように分かりやすく解説します。
・傾向分析: 過去問を複数年分解くことで、出題傾向や頻出分野を分析し、重点的に学習すべき箇所を把握します。
・模擬試験: 過去問を本番同様の環境で解くことで、模擬試験として活用し、実力試しを行います。
模擬試験について
幼児教室や専門塾で実施される模擬試験を、月に1~2回の頻度で受験します。
模擬試験は、以下の目的で活用しましょう。
・実力試し: 現在の学力レベルを把握し、 得意な箇所と弱点を分析します。
・時間配分: 実際の試験時間を意識し、時間配分を練習します。
・精神面の強化: 試験本番を想定した環境に慣れることで、緊張感を和らげ、落ち着いて試験に臨めるようにします。
よく言われることですが、
模擬試験は本番の気持ちで
本番は模擬試験の気持ちで取り組めるよう、
日々の模擬試験に緊張感をもってチャレンジしましょう。
模擬試験の結果は、今後の学習計画に反映させましょう。
具体的には、以下の点に注意します。
・弱点克服: 苦手な分野や問題形式は、重点的に復習します。
・得意分野の強化: 得意な分野は、さらに伸ばせるように、応用問題にも挑戦します。
・時間配分の見直し: 時間配分に問題がある場合は、解く順番や時間の使い方を工夫します。
親の受験準備
1.面接対策: 自己紹介や家族の力量を表現
親の面接では、自己紹介や家庭の教育方針を具体的に話せるよう準備が必要です。
たとえば、「家庭で大切にしていること」を具体例を交えて話す練習をすると効果的です。
また、質問に対して簡潔かつ自信を持って答えられるよう、夫婦間で模擬面接を行うことも有益です。
2.環境作り: 学習にちゃんと取り組めるスペース
子どもが学習に集中できる環境を整えましょう。
例えば、静かで明るい学習スペースを用意し、子どもが使いやすい机や椅子を選ぶことが重要です。
また、親が一緒に学習に付き合う時間を決めることで、学習へのモチベーションを高めることができます。
4. 小学校選びのポイント
学校ごとの出題傾向を把握
•各学校のカリキュラムを調査
•情報集めはオープンスクールや説明会で
小学校を選ぶ際には、まず各学校の出題傾向やカリキュラムを把握することが重要です。
例えば、ある学校では図形や数の基礎知識を重視する一方で、別の学校では協調性やリーダーシップを重視する場合があります。こうした情報は、学校説明会やオープンスクールに参加することで得られます。
また、過去の受験問題集や学校のパンフレットを参考にするのも有効です。
具体例として、ある学校では「自由遊び」の観察を通じて子どもの創造力や社会性を評価します。
このような情報を事前に知っていれば、日常生活の中で自由遊びを取り入れるなど、適切な準備が可能です。
自分の家庭に合った学校を選ぶ
学校選びの際は、子どもだけでなく家庭全体の状況に合った学校を選ぶことも大切です。
例えば、課題学習を重視する学校であれば、家庭での学習習慣をしっかり整えておく必要があります。
一方、体育活動や芸術活動に力を入れている学校を選ぶ場合は、子どもの興味や得意分野に応じた準備が求められるでしょう。
具体例として体操や絵画が得意な子どもがいる家庭では、芸術教育に力を入れている学校を選ぶことで、子どもの能力を最大限に活かせます。
また、大学受験を見据えてよりレベルの高い中学校を受験することを予定しているなら、しっかり学習をサポートしてもらえる環境や私立中学校への推薦のある小学校を選ぶべきです。
通学の便利性を検討
学校の教育内容や特色だけでなく、通学の便利性も見逃せないポイントです。
特に毎日の通学が負担にならない距離やアクセスの良さを確認しましょう。
具体例として電車やバスでの通学が必要な場合は、通学路の安全性を確認したり、朝の時間に通学シミュレーションを行ったりすることが役立ちます。
一見すると、通学に難しそうなエリアに見えても送迎バスを出している小学校はたくさんあります。
これにより、子どもが無理なく通学できる環境を整えることができます。
5. 小学校受験の注意点
よくある失敗例3選
子どもの負担を無視した詰め込みスケジュール
小学校受験で多くの親が陥りがちな失敗のひとつは、スケジュール管理の乱れです。
たとえば、準備を開始する時期が遅れたり、過密なスケジュールで子どもに負担をかけてしまうケースがあります。
具体的には小学校受験のために、多くの習い事をさせたり、学習時間を増やしすぎたりした結果、子供が疲れてしまい、学習効果が上がりませんでした。
これを防ぐためには、あらかじめ年間計画を立て、無理のないペースで進めることが重要です。
あくまで小学校受験をするのは幼稚園児という小さな子どもなんだということを忘れず、学習と遊びのバランスを取りつつ、定期的に進捗を確認する時間を設けると良いでしょう。
小学校受験塾を活用せず親だけで乗り切ろうとする
また、もう一つの失敗例として、準備が家庭内だけで完結してしまうことが挙げられます。
例えば、模擬試験や外部の塾など、外部リソースを活用せずに進めた結果、試験本番で子どもが緊張しやすくなったり、他の子どもと比較した際に差が出てしまうことがあります。
これを回避するためには、模擬試験や専門家のアドバイスを取り入れることが効果的です。
適当な幼児教室の選び
当初、自宅から近いという理由で幼児教室を選びましたが、子供の性格に合わず、学習意欲が低下するということはよくあります。
大人と違って子どもには受験の意味を説明するよりも、楽しく学んで気づいたら合格するレベルに達していたというように誘導していくことが肝心です。
だから子どもが楽しんで通える幼児教室に変えたことで、学習意欲が向上するということもよくあります。
親の焦り
小学校受験が近づくにつれて、親が焦ってしまい、子供にプレッシャーを与えてしまうこともよくあります。
是が非でも合格させたいという親の気持ちは、緊張感となって子どもに伝わります。
それは幼稚園児には重すぎる負担です。
親は俳優になったつもりで笑顔をキープして、イライラや焦りを子どもにぶつけないようにしないといけません。
親の態度や言動に注意
安心できる家庭環境は子どもの成績に大きな影響を与えます。
親の態度や言動は、子どもの受験準備に大きな影響を与えます。
例えば、親が朝の起床時間をしっかり守ることで、子どもに規則正しい生活リズムを教えることができます。
また、子どもに対して公平で一貫性のある態度を取ることも重要です。
たとえば、「兄弟の中で特定の子どもだけを特別扱いしない」など、家族全体で協力し合う姿勢を見せることで、子どもは安心感を得られます。
さらに、親自身が過度にプレッシャーを感じると、その感情が子どもに伝わり、逆効果を招くことがあります。
受験はあくまで子どもの成長を見守る一環と捉え、無理なくサポートする姿勢を心がけましょう。
6. 専門家や塾を活用するタイミング
塾選びの基準は指導力と情報力
専門家や塾を活用する際の重要なポイントは、その塾が専門的な知識や実績を持っているかどうかです。
例えば、志望校ごとの出題傾向を熟知し、それに沿った指導ができるカリキュラムを提供している塾は信頼できます。また、個別指導や少人数制など、子どもに合ったサポート体制が整っている塾を選ぶことも重要です。
具体例としてある塾では、志望校ごとに模擬試験を実施し、各校の傾向に沿ったフィードバックを提供しています。
こうした情報をもとに、子どもの弱点を効率よく克服することが可能です。
家庭学習との連携
塾を活用する場合でも、家庭学習との連携が不可欠です。
例えば、塾で教わった内容を家庭で復習する時間を設けることで、知識の定着を図ることができます。また、家庭でしかできない学習方法、例えば親子で楽しむ言葉遊びや自由研究なども並行して行うことで、バランスの取れた学習環境を構築できます。
最も効果的な方法の1つは、子供の興味関心を活かした学習と親子で一緒に楽しく学習することです。
例えば、子供が電車に興味を持っていた時期には、電車の図鑑を見ながら、路線図を覚えたり、駅名をひらがなで書いたりする学習を取り入れます。
また、数字に興味を持っていた時期には、お菓子を数えたり、お買い物ごっこをしたりしながら、数の概念を学ぶようにします。
このように、子供の興味関心を活かすことで、学習意欲を高め、効果的に学習を進めることができます。
また、親子で一緒に学習に取り組むことで、子供とのコミュニケーションが増え、信頼関係を築くことができ、親が楽しそうに学習に取り組む姿を見せることで、子供も自然と学習意欲を高めることができるようになります。
塾と家庭の密な連携
塾に丸投げするのではなく、家庭との密な連携が大切です。
例えば、塾の先生と親が定期的にコミュニケーションを取り、子どもの学習状況や性格に合ったアプローチを相談することが効果的です。また、塾での学びを家庭で補完する体制を作ることで、子どもの成長を総合的に支えることができます。
具体例として定期的な面談で塾から学習プランの提案を受け、それを家庭で実行に移す際の進捗を親が確認する体制を整えることで、子どもに適切なサポートを提供できます。
【完全ガイド】小学校受験対策に必要な準備と注意点を詳しく解説:まとめ
小学校受験の対策は、親子両方の準備が重要ですが、
ズバリ申し上げますと、
小学校受験は親が10割とお考えください。
幼稚園児の自発的な学習や弱点克服などできるはずがありません。
逆算で考えて余裕を持って早い時期から始めて、スケジュールに合わせた対策をこなしていきましょう。
また、どんな小学校があるのかは2~3歳のころか確認し、学校見学や文化祭などに足を運んで、情報集めを忘れずに行いましょう。
そして、できるかぎり積極的に専門家や幼児教室などの小学校受験塾を活用しましょう。
親は子供のことを一番良く知っている立場ですが、
受験については小学校受験塾がプロです。
うまく連携して子どもの将来にとって最善の選択を行えるようにしましょう。