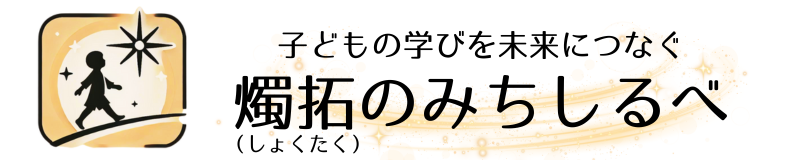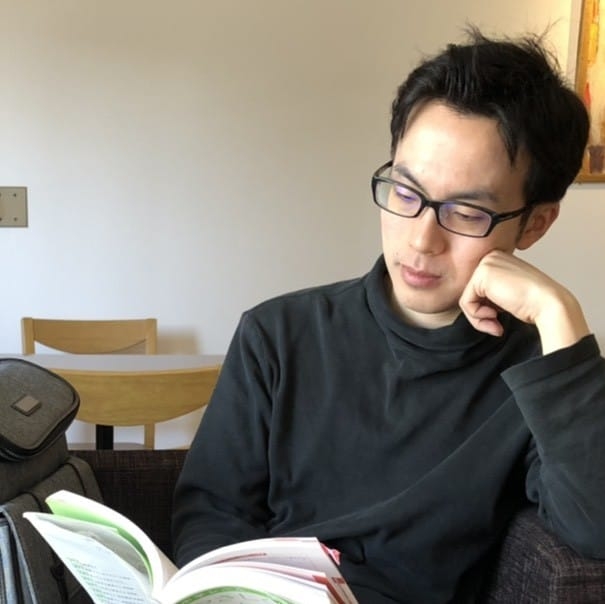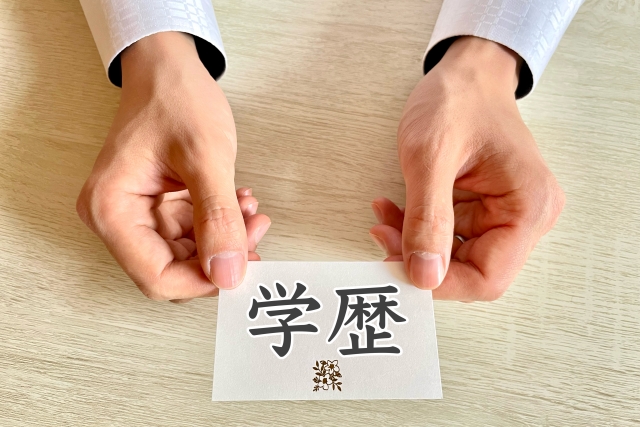勉強って何のためにするの?
中学生や高校生のお子さんをお持ちの方なら、一度はこんな質問をされたことはあるんじゃないでしょうか?
親として、どう答えたらいいのか迷ったんじゃないでしょうか?
特に

学校の勉強なんて社会に出ても役に立たないじゃん
と言われると、「確かに…」と思ってしまうこともありますよね。
この記事では、
子どもから「勉強の本当の意味」を尋ねられた際に、
わかりやすく、勉強への意欲が湧く説得力のある伝え方をご紹介します。
勉強の意義を伝えられるようになることで、
子どもが自ら学ぶ姿勢を持つきっかけ作りをサポートします。
子どもの疑問にどう向き合うか
「どうして勉強しなきゃいけないの?」
この問いは、多くの大人も子ども時代に同じ疑問を抱いた経験があるのではないでしょうか。
少なくとも私も同じように考えていました。
「父や母ですら仕事で絶対に使っていないであろう勉強の知識をなぜ学せようとするんだろう??」
そう思って親に尋ねてみると、
「黙って勉強しろ!」
の一点張りで話になりません。
学校や塾の教師に聞いても
「社会に出たときの基礎知識になるから」
とあいまいな説明しかしません。
おそらく話している本人すら、
勉強の意味を理解していないんだろうなと
子供心に気づいていました。
それでも、多くの保護者が
「大学までは行ってほしい」
「勉強しておいた方が将来役に立つ」
と考えているのは、
決して悪気があるわけじゃなく、
子どもの将来をより良いものにしたいという親心があるからです。
しかし、
子どもに「勉強する意味」を納得させるためには、
単なる「将来のためだよ」という抽象的な言葉では不十分です。
子どもが「なぜ勉強するのか」を理解するには、
より具体的な例や考え方を提示する必要があります。
そして、それを伝える前に、
まず大人自身が「なぜ勉強するのか」という意味を再確認しておくことが重要です。
また、
「勉強する意味」を子どもに理解させるだけでは不十分です。
「勉強する意味」を理解させる理由は、
勉強への意欲を高めて、
より良い中学校、高校、大学へ進学しようという「意欲」を湧き立たせることがポイントです。
勉強への意欲を高めて、
より良い学校へ行きたいという意欲を湧き立たせるための
説明する方法を順に解説していきます。
________________________________________
第1段階:勉強をしなかった場合を考える
まず、「勉強をしなかった場合」を想像してみてください。
学校で基礎的な科目を学ばなかったとしたら、
どのような状況に直面するでしょうか?
•算数や数学:
買い物で合計金額、消費税、得られるポイントが計算ができない。
目的地に到着するまでの時刻が推測できない。
•国語:
相手の話している内容を正しく理解できず、人間関係で悩むことになる。
仕事での約束事である契約書や重要な書類を理解できず、無駄にお金を失うことになる。
•社会:
都道府県の場所や気候が分からず、旅行を楽しめない。
選挙や税金などの制度を知らず、損をしていることにも気付けない。
これらの問題は、
学校を卒業した後に社会で大人として独り立ちして生きるための基礎力が欠けている場合に直面する現実的な問題です。
「勉強なんて役に立たない」と考えている子どもに対しては、
このように子どもの目線に立って具体例を挙げながら勉強しないことのリスクを
少しずつ理解させることが、
勉強の意味を理解するための第1歩です。
子どもへの具体的な伝え方の会話例
子どもに勉強する意味を伝える際には、
「勉強をしなかった場合」を具体的なエピソードや話で伝えると効果的です。
1. 家庭内の身近な例を挙げる
例えば、家計管理や日々の生活の中で勉強がどのように活かされているかを示しましょう。
「例えば、今晩の夕食を作る時、スーパーでいくらの予算内でどれくらい買えるか計算するよね。これが算数の力だよ。」
「家計簿をつけて収支を確認するのも勉強で学んだことが役立っているんだ。」
2. 保護者自身の体験を話す
子どもは親の体験談に耳を傾けやすいものです。
「私も学生の頃、歴史の勉強が嫌いだったけど、
社会に出てから海外の人と取引するようになって、
日本の歴史を聞かれた際、答えられなかったんだ。
外国では自分の国については本当に詳しく知っているのに、
なぜ日本人は学ばないんだ?
と言われて本当に恥ずかしかった。
『学生の頃にちゃんと歴史をマンで置けばよかった』って心から思ったよ。」
このように経験に基づいた話をできれば、
より勉強の意味を実感できるようになります。
________________________________________
第2段階:勉強することで得られる幸せな人生を得られる具体例を子どもに伝える
勉強の意義を説明するためには、抽象的な話よりも具体例が効果的です。
以下のポイントを子どもに伝えてみましょう。
勉強は未来の職業の選択肢を広げる手段であることを伝える
平均年収が高い職業といえば、
医者、弁護士、会社経営者です。
その中で、
医者だけは、学校の勉強の成績が良い人だけがなれる職業です。
なぜそうなっているのか理由を説明すると、
年収が高い医者になりたい人は、
たくさんいます。
でも、
日本中の人が医者になると社会がまわりません。
そこで、
成績の良い人だけが医者になれる仕組みが出来上がっているんです。
このように学校の科目そのものは、
医者になって使う機会があまりなかったとしても、
勉強の成績を基準として上位層だけが医者になれるという仕組みがあるので、
勉強は「未来の準備」と言えます。
なお、
学校の科目そのものは医者になって使う機会があまりないと書きましたが、
数学は研究医には必須ですし、
生物は医学の基礎学力となりますので、
役に立たないというわけではありません。
勉強は思考力や問題解決力を育てる
勉強は暗記ばかりではありません。
問いかけに対して解をだしたり、
解が正しい理由を証明したりと頭を使って論理的に考える問題もあります。
そういった、ただの知識だけじゃなくて、
考える訓練は、物事が正しいかどうかを考えたり、
課題を解決する力も身につきます。
例えば数学は、
日常での計算だけでなく、論理的に考える力を育てますので、
ある程度、数学を学んでいれば、
「ねずみ講」や「マルチ商法」に騙されにくくなります。
こういった勉強することで得られる幸せな人生を得られる具体例を
ちゃんと子どもに話せるようになりましょう。
社会で役立つ勉強がどのように使われているのかの実例を説明する
多くの子どもが、学校で学んでいる内容が社会でどのように役立つのか想像できず、
勉強する意味に疑問を抱くことがあります。
このようなときには、
具体的な事例を挙げて勉強の重要性を伝えることが効果的です。
次のパートでは、数学、歴史、英語を中心に、社会でどのように学びが活かされるのかを具体例を交えて説明します。
3. 社会で役立つ勉強の実例
1. 数学:建築士やエンジニア、医療分野での計算やデータ分析に不可欠
数学は、多くの職業で欠かせないスキルです。その具体的な役立ち方を子どもに伝えることで、数字や計算への興味を持たせることができます。
建築士やエンジニア
建築士が家やビルを設計する際には、数学の知識が必要不可欠です。
例えば、建物の耐久性を計算するには力学の知識、柱や梁の長さを正確に計算するには幾何学のスキルが求められます。
「例えば、建物の柱の太さを間違えると、その建物が地震で倒れてしまう可能性があるよね。だから正確な計算がとても大切なんだ。」
また、エンジニアはプログラムや機械の設計で膨大なデータを分析し、最適な結果を導き出す必要があります。これも数学がなければ成り立ちません。
医療分野
医療現場では、薬の分量や治療計画のデータ分析に数学が活用されています。例えば、薬剤師は患者の体重や年齢に応じて薬の適切な量を計算しますし、医師は統計データを使って新しい治療法の効果を評価します。
「薬を正確に出すためには計算が必要なんだ。もし間違えると、患者さんの命に関わるよ。」
2. 歴史:過去を学ぶことで、未来を予測し計画を立てる力がつく
歴史の授業では、戦争や文化、経済の発展など過去の出来事を学びますが、これが社会でどのように活かされるのかを具体的に伝えることが重要です。
経済やビジネスの分野
歴史を知ることで、過去の成功や失敗を分析し、未来の計画に役立てることができます。例えば、経済学者は過去の景気変動を研究し、それを基に現在の経済政策を提案しています。同じように、企業も過去の市場動向を参考にして新しい商品やサービスを開発します。
「例えば、過去に流行った商品を調べることで、次に何が売れるかを予測することができるんだ。」
国際関係や政治
また、歴史は国際関係にも深く関わっています。国と国との関係を理解するには、過去の戦争や条約について学ぶことが欠かせません。例えば、外交官は歴史の知識を駆使して他国と交渉を行います。
「過去の歴史や政治の安定性、民族間の対立や資源の状況などを学ぶことで、
戦争がどうして起きたのかをある程度理解できます。
すると、同じ失敗を繰り返さないためにはどうしたらいいか考えられたり、
どうすれば戦争を止められるかの解決方法が見つかりやすくなるんだ。」
3. 英語:グローバルな仕事や旅行など、世界を広げるツール
英語は、世界共通の言語としてさまざまな場面で役立ちます。英語を学ぶことは、単に外国語を話せるようになるだけではなく、視野を広げ、グローバルな世界で活躍するための鍵となります。
海外で働く夢を叶える
例えば、国際的な企業で働いたり、海外で自分のビジネスを展開したりするには英語が必須です。英語を話せることで、外国のクライアントと直接交渉ができ、ビジネスチャンスを広げることができます。
「例えば、海外の会社でゲームクリエイターとして働きたいなら、英語が話せないと会議に参加できないよね。
その他にも、今の世界はアメリカから最新情報が発信されることが多い。
すると、英語の原文を読めないとライバルに負けてしまうことになる。
だから話す聞くだけでなく、読めることも大事なんだ。」
旅行や日常生活
旅行の場面でも英語が役立ちます。飛行機の乗り換えで迷ったときやレストランで食事を注文するとき、英語を話せると世界中どこへ行っても困りません。
「海外旅行で道に迷ったときに英語で話しかければ、現地の人に助けてもらえるよ。」
国際的な文化や情報に触れる
また、英語を通じて、世界中の文化や情報にアクセスできます。映画や音楽、ニュースなどを英語で直接楽しむことができれば、より深い理解が得られるでしょう。
「例えば、映画を字幕なしで楽しめると、登場人物がどんな風に話しているかリアルに感じられるよ。」
子どもが勉強の科目に興味を持ちやすい伝え方は説明ではなく質問形式
これらの具体例を通じて、子どもに「勉強が役立つ瞬間」をイメージさせることが大切です。
例えば、次のような質問をして、子ども自身に考えさせてみるのも良いでしょう。
•「好きなゲームを作るにはどんな勉強が必要だと思う?」
•「海外のサッカー選手と話したいときに、どうすればいいと思う?」
•「もし家計の計算を間違えたらどうなるかな?」
「本当に勉強が役立つの?」という疑問に対して、具体的な社会での活用例を示すことで、子どもに勉強の意義を理解させることができます。数学、歴史、英語など、どの教科も将来に繋がるスキルを育むための大切な学びです。
「これが君の未来を作る道具になるんだよ。」
そんなメッセージを添えて、子どもに勉強の価値を伝えてみてください。
具体的な質問形式の会話例を紹介します。
________________________________________
実践的な子どもへの勉強する意味の伝え方の会話例
実際に子どもから「どうして勉強するの?」と聞かれたとき、どう答えるか迷いますよね。以下の会話例を参考にしてください。
•会話例1
子ども:「算数なんて将来使わないよね。」
親:「本当に使わないかな?
今日、買い物したときにポイントっていくらもらったっけ?
例えば計算ができないと損しちゃうよ。」
•会話例2
子ども:「微分積分って使ってる人を見たことないんだけど?」
親:「今、AIがブームになってるよね?
AIってどういう仕組みで回答を出しているか分かる?
過去の情報から確率的に高いものを引っ張り出してるんだよ。」
•会話例3
子ども:「何で学校で歴史を学ぶの?」
親:「●国と▲国はよく紛争するよね?
どうやったら解決できると思う?
それを知ろうとしたら争うようになった原因を知らないといけないよね。
歴史を学ぶことで、両国の立場や考え方を理解できるようになるから
現実的な解決策が考えられるようになって、
同じ失敗を繰り返さないためにどうすればいいか分かるんだ。」
•会話例3
子ども:「漢字が苦手なんだけど、嫌いな教科もやらないとダメ?」
親:「そうだね~。
漢字は知らないと、恥をかくことが多いんだけど分かるかな?
例えば、
先日、「出汁」を「でじる」って読んだり、
「葉酸」を「はさん」と言ったりしてる大人がいたんだ。
そういう間違った読み方をしてると信頼を失くしちゃって、
人間関係もうまくいかなくなっちゃんだ。
逆にこういった、苦手なことでも挑戦することで、
できるようになったら信頼を得られるだけじゃなく、自信がつくよ。」
かなりシンプルに書きましたが、
いきなり答えを話すんじゃなくて、
こんな感じで、質問形式にすることで子どもにも勉強する意味を考えるキッカケを与えられれば、
より真剣に考えて腹落ちできるようになります。
_______________________________________
勉強は人生を生きやすくする最強のゲーム
このパートでは、
勉強についてキレイごと抜きのぶっちゃけで書いてみたいと思います。
勉強は時に「辛いもの」「やらなければいけないもの」と感じられることがありますが、実際には人生をより生きやすくするための「最強のゲーム」と言えます。このゲームに挑むことで、より多くの選択肢を手に入れ、困難を乗り越える力を得ることができます。ここでは、勉強がどのように人生を豊かにするか、3つの具体例を挙げて説明します。
1. 採用試験に合格しやすくなる
勉強をすることで、就職活動や転職活動の際に有利になることは明白です。特に、企業が行う採用試験や筆記試験では、基礎学力が問われる場面が多くあります。
筆記試験で基礎力を発揮する
多くの企業が採用試験として行う「一般常識テスト」や「適性検査」では、国語、数学、英語など学校で学ぶ内容がベースになります。たとえば、数学が得意であれば、数的処理問題や統計の理解が求められる問題にスムーズに答えられます。また、国語力が高いと、ビジネスメールの作成や資料の要約が得意になり、仕事でも高く評価されます。
「ある就職活動中の学生は、適性試験で高得点を取り、競争率の高い大手企業に内定しました。その背景には、日々の勉強で培った基礎力があったのです。」
昇進やキャリアアップにも有利
さらに、勉強を続けることで昇進試験やキャリアアップの際にも有利です。例えば、公務員の採用試験では、法律や経済の知識が問われます。これらの知識をしっかり学んでおけば、競争の激しい試験でも頭一つ抜け出せます。
2. 難関資格を取得しやすくなる
資格取得は、勉強が直接的に人生を変える場面の一つです。特に難関資格は高い専門性を求められますが、その分、取得することで人生の選択肢が大きく広がります。
具体例:医師や弁護士などの専門職
すでに上でも書きましたが例えば、医師になるには、医学部に進学する必要があります。
そのためには高い偏差値が必要です。
逆に言えば、勉強さえできれば誰でも医学部に合格できるんです。
また、膨大な量の医学知識を学ぶ必要がありますが、
受験勉強で培った勉強のコツさえわかっていれば国家試験にも合格しやすくなり、医師として働く道が開け、高収入や社会的な信用を得ることができます。
同じように、弁護士でもロースクールや予備試験を受験するには、法律だけではなく一般教養として数学や英語や歴史、経済などの知識が必要になってきます。
つまり勉強ができると弁護士になれる確率が高くなるんです。
だから学生のうちにしっかりとした勉強したことは無駄にはならないどころか、非常に大きなアドバンテージになります。
子育てや趣味にも役立つ資格
また、難関資格だけでなく、FP(ファイナンシャルプランナー)や簿記のような資格も、日常生活を豊かにするために役立ちます。例えば、FPの資格を持っていれば、自分や家族の資産運用を効率的に行えるようになり、家計の管理が楽になります。「家計の見直しをして、貯金が50万円増えた」という実例もあります。
勉強を通じて得た資格は、人生の武器となり、自分の価値を高めるのです。
3. 噂やスピリチュアル系にだまされにくくなる
勉強をしていると、物事を論理的に考える力が身につきます。この力は、情報が溢れる現代社会で非常に重要です。特に、ネット上の噂やスピリチュアル系の話に対して冷静に判断できる力は、人生を生きやすくする上で欠かせません。
具体例:デマ情報に振り回されない
例えば、インターネット上で「〇〇を飲むだけで痩せる」や「この投資にお金を入れれば絶対儲かる」といった広告を目にしたことがあるでしょう。勉強している人は、こうした情報を鵜呑みにせず、「本当に科学的根拠があるのか?」と疑問を持つことができます。統計やデータを学んでいれば、数字の裏に隠された意図を見抜く力もつきます。
スピリチュアル商法にも強くなる
また、「運が良くなる石」や「幸せを呼ぶ絵画」といったスピリチュアル商法に引っかかる人がいますが、勉強している人は「証拠や根拠のない話」を論理的に分析できます。その結果、不必要なものにお金を使わず、自分の目標に集中することができます。
「例えば、ある主婦が勉強を通じて消費者心理や統計学を学んだ結果、怪しいセミナーに勧誘された際に断る理由を明確に説明でき、無駄なお金を使わずに済んだというエピソードがあります。」
________________________________________
勉強は人生を楽にクリアするチートスキルとして楽しむ
勉強は「単に知識を詰め込むだけ」の作業ではありません。それは人生を攻略するための「最強のゲーム」です。このゲームに挑戦することで、社会で成功する力や、困難を乗り越えるスキルを手に入れることができます。
•採用試験に勝つスキルを得る:筆記試験や面接で他者よりも優位に立つ。
•難関資格で人生の選択肢を広げる:専門知識を武器に、豊かな生活を実現する。
•情報を冷静に分析する力を持つ:嘘やデマに惑わされず、賢い選択ができる。
勉強を「嫌なもの」として避けるのではなく、「ゲームクリアを目指す挑戦」として楽しむ姿勢を持つことで、人生をさらに楽しく、豊かなものにすることができるでしょう。
子どもの勉強への疑問に向き合うには親の姿勢が大切
最後に、子どもに「勉強の本当の意味」を伝えるために、保護者としてできることを考えましょう。
•共に学ぶ姿勢を見せる
親は子どもに勉強しろというけど、
親はテレビやゲームをしてばかり・・
残念ですが、それだと子どもは勉強する意欲が上がりません。
子どもは親の言葉で育つのではなく、
親の背中を見て育ちます。
だから、
子どもと一緒に課題を解いたり、
興味のあるテーマを共有したり、
子どもと一緒に勉強するするなどして、
親も頑張っているという姿勢を見せましょう。
•学ぶ楽しさを伝える
結局、勉強する意味を問う子どもは学ぶ楽しさが分からないことが原因です。
だから、「この知識がこう繋がるんだ!」という発見、
難しい問題を解けた楽しさ、快感を味わえるようになると、勉強のイメージがポジティブになります。
直接、勉強を教えられる必要はありません。
ただ、子どもに勉強を丸投げするんじゃなくて、
親として、わからない問題がでてきたときにはどう対処すればいいのか、
挫けそうになった時にどのように励ますのか
そういったことはあらかじめ考えておく必要があります。
子どもの「どうして勉強するの?」という問いに正面から向き合うことは、
親としての信頼を得るためにも重要です。
たとえ完璧な答えを持っていなくても、
「一緒に考えよう」という姿勢を見せるだけで、子どもは安心感を持ちます。
これまでに挙げた具体的な例や、自分の経験談を交えながら対話をすることで、子どもに納得感を与えることができるようになり、勉強への意欲も高めやすくなるはずです。
勉強する本当の意味を聞かれた際の答え方のまとめ
子どもが「勉強の本当の意味」を知ることができれば、学びに前向きになるきっかけになります。
「勉強は未来への投資」という考え方を共有しつつ、親も一緒に学びの姿勢を見せることで子どもの将来をサポートしていきましょう。
ぜひお子さんと向き合う時間を大切にしてください。
この記事がお子さんの勉強の意欲向上につながれば幸いです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。